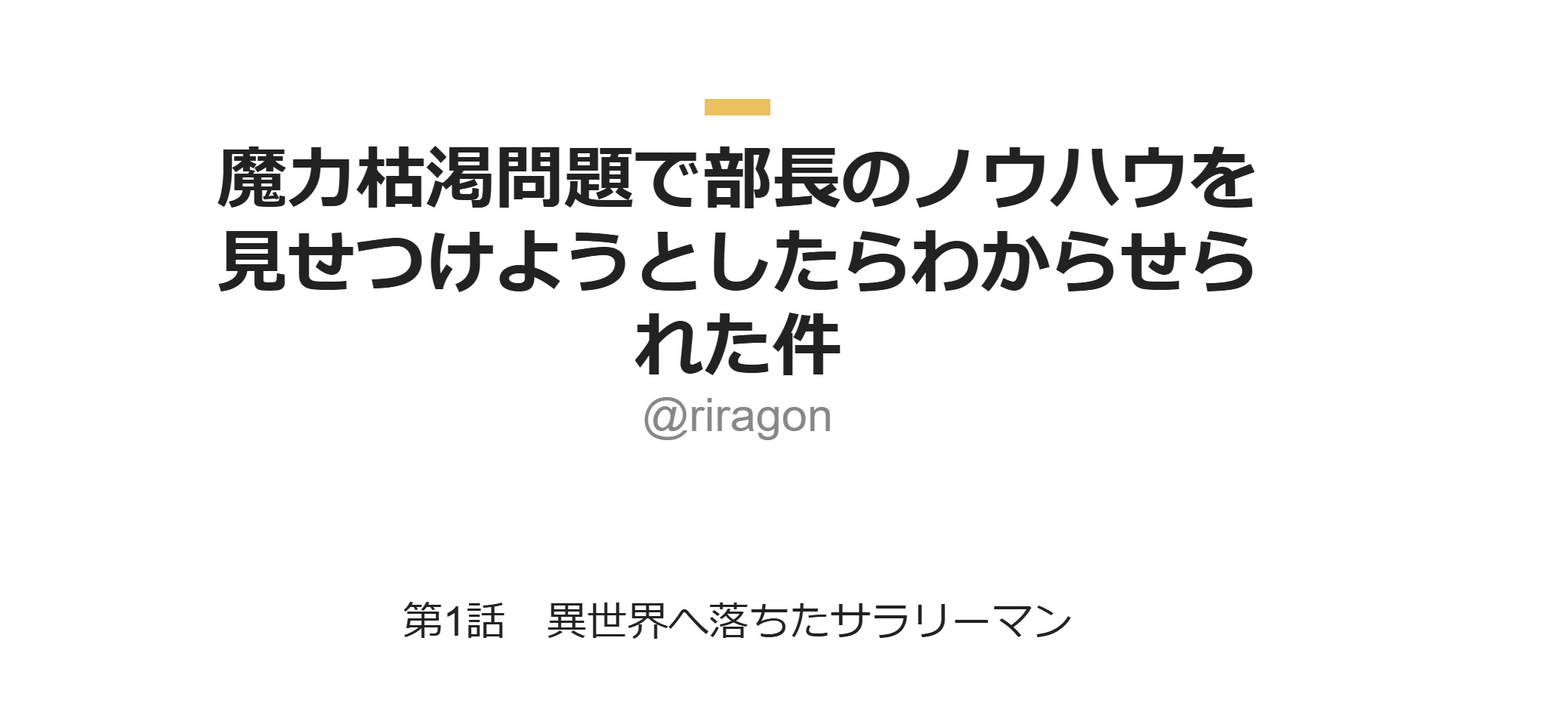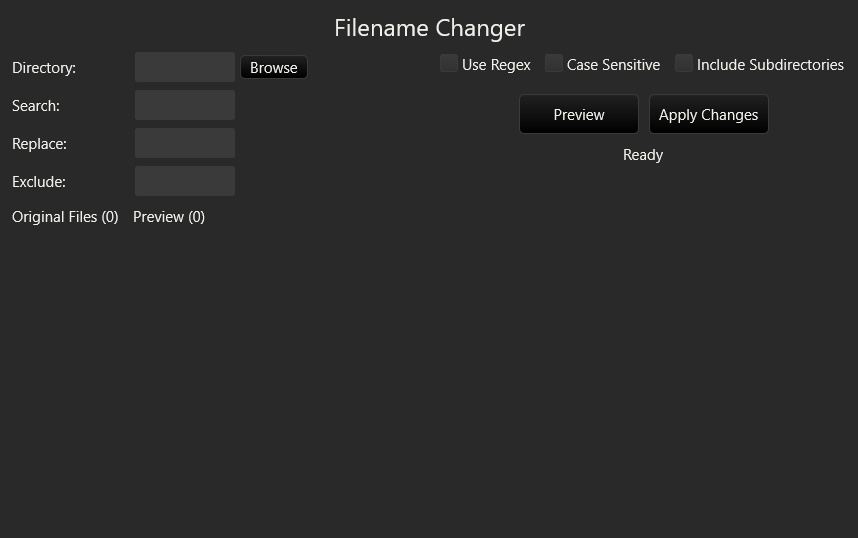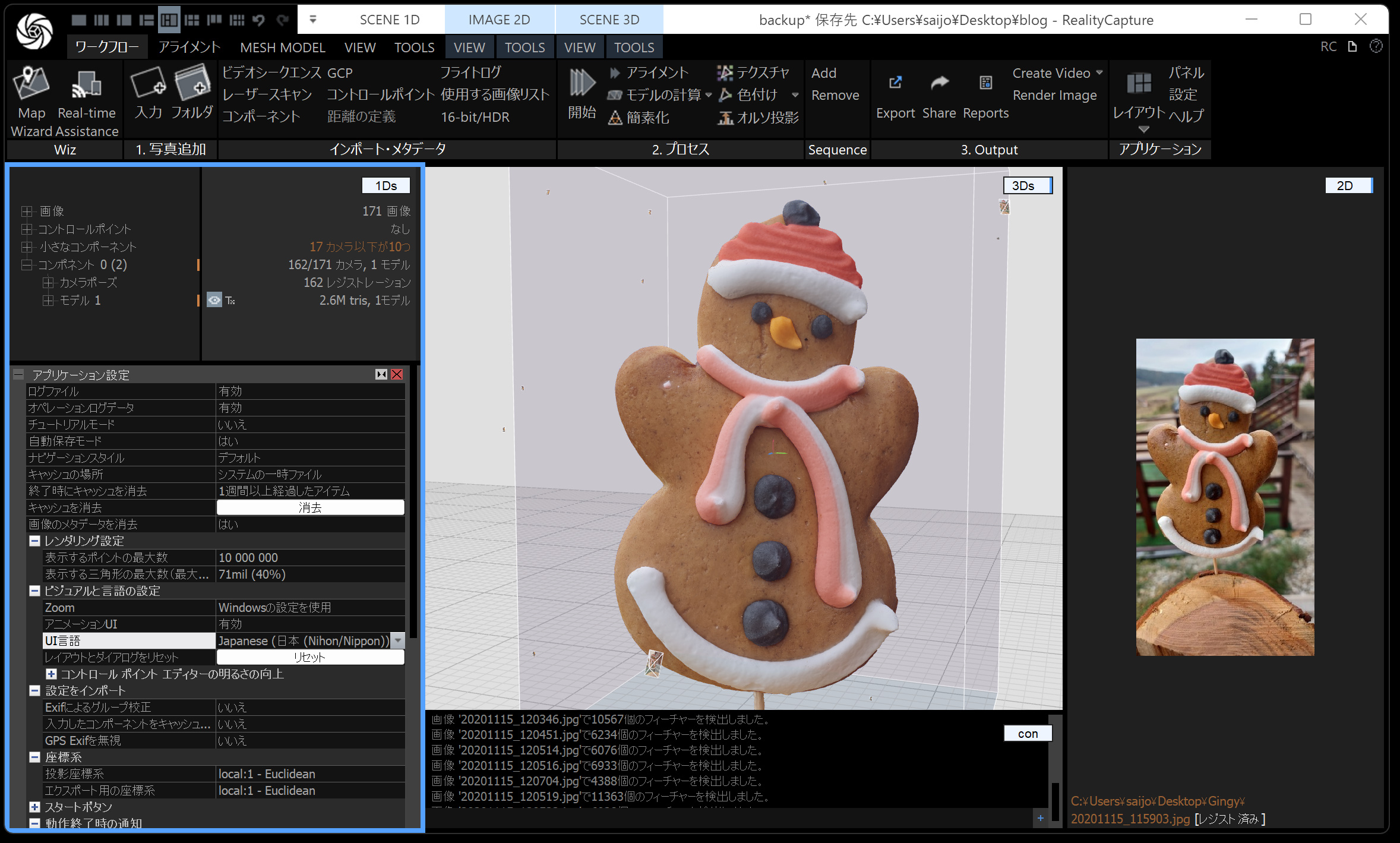AIと人間の文章は、もはや見分けがつきません。手書きかワープロかを比較した時代のように、もうすぐAIで書いている文章かどうかも問わない時代になると感じた件です。
最近の大規模言語モデル(LLM)の進化は目覚ましく、AIが生成する文章と人間が書く文章の区別がほとんどつかなくなっています。私自身もAIの進化を日々感じていてOpen AI社のO1 ProやAnthropicのClaude 3.7などの最新モデルを使用していますが、それでも今回の試したことには驚きました。
AIによる長文作成の従来の課題がありました。AIによる文章生成、特に小説などの長文には明確な弱点があります。このような問題はLLM、生成系AIの特徴とされてきましたが、少し工夫をすれば問題が大幅に改善されています。
話の筋が途中で矛盾する
登場人物の設定や名前が突然変わる
物語の展開が停滞する
似たような内容が繰り返される
私は実際に、約2万文字・4章構成の小説「魔力枯渇問題で部長のノウハウを見せつけようとしたらわからせられた件」をAIに生成させました。結果は驚くべきもので、最初から最後まで一貫したストーリーラインを維持し、前述のような矛盾点が見られない作品となりました。それでも書き直したり修正したり1日かかっていますが、人間なら2週間は必要です。
作品は「カクヨム」プラットフォームで公開しています。
https://kakuyomu.jp/works/16818622170655777234/episodes/16818622170656589763
AI臭さを探してコメントしてみてください。
この小説を複数のAI文章判定システムで分析しましたが、AIによる生成だと見抜くことができませんでした。確かに「転生系」などの特定ジャンルでは、人間が書く文章もある程度パターン化されているため区別が難しいという側面もあるでしょう。人間もクソみたいな文章を書きますから、クソの中にクソがあるとそれが犬か人間かなど見分けがつかないのと同じです。
2万文字の文章を生成してAIの癖に気が付いたこと
現状でも、AI生成文章には以下のような特徴が見られました。普通の小説より多く多用される印象です。この部分に注目して文章を見ると、なろう系小説においてAIかどうか疑えるかもしれません。でも学習に使われたデータにそれらの出現度が高かったのでしょう。便利なので素人小説によく使われそうです。
三点リーダー(「…」)の多用
感嘆符や疑問符の過剰な使用(「!?」など)
これらの特徴は校正(これもAIを活用)によって容易に除去できます。AIに構成するときにそれらはできるだけ削除してと指示するだけです。
2万文字の文章を一貫させるために工夫したコツが以下です。
事前準備の充実:世界観やアイデアを明確に設定する
キャラクター設定の詳細化:登場人物の性格や背景を具体的に決める
シーン割り(脚本)の作成:物語の流れを事前に構造化する
適切な分量設定:一度に生成する文章を適切なサイズ(例:5,000文字程度)に区切る
物語の作り方を分析をしまして、初めにアイデア世界観の情報→キャラクター→800文字プロットを作り、面白いプロットができるまで世界観とキャラクターの修正を繰り返しました。
プロットが出来たら、アイデア世界観、キャラクターの情報を元に物語の構造を作りました。この構造まで作ると、AIが作った第2章はつまらない、第3章は物語が停滞する。などが見えてきます。人間がちょっと構造を作り変えて、変化のある構造にします。
その構造を元にシーン割り(脚本)を作り、シーンや登場人物を配置して明記してゆきます。シーン割り(脚本)を元に文章を出力させるとバランスの良い文章になりました。
プロット、構造、シーン割り(脚本)ですが、同じような内容が3つあることで、最後の第4章を書くときにとても混乱しました。シーン割り(脚本)が出来たらプロット、構造は捨てたほうがよいのかもしれません。もしくは構造だけで十分かもしれません。
これらの工夫により、AIによる文章生成で起こりがちな問題を大幅に減らすことができます。それぞれtxt形式にでもして、LLMに文章を作ってもらうときに投げ込むだけです。
AIによる創作支援ツールは日々進化しており、今後もさらに人間の創作との境界が曖昧になっていくでしょう。こうした技術をどう活用していくかは、これからのクリエイティブ分野における重要な課題となっていくと考えられます。